気がつくと、白い男が窓辺に腰掛けて、小説家を見下ろしていました。

 |
|
「そんなに怖がらないで?今から聞いて欲しいことがあるんだ。」 |
「まず、きみの鳥は無事だよ。現に君と一緒に食事をしてた。」
白い男は、妙に穏やかな口調でした。
でも、話が見えてきません。
「君が血相を変えて僕を探してくれていて、とても嬉しかった。
いつも、僕のことなんて、考えてないと思ったから。」
「君を見つめながら食事がしたかったんだ。…君は苦痛だったかもしれないけれど。」
小説家は、はっとしました。
まさか、まさか。この男は…。
「それから、この3日間の事を小説として書くんだ。誰かに見せればきっと良いことが起きるから。」
|
間違いありませんでした。
「僕はそろそろ小鳥に戻るよ。また、鳥籠で僕を飼ってね」
残された小説家は、言葉になりませんでした。
|
 |
 |
|
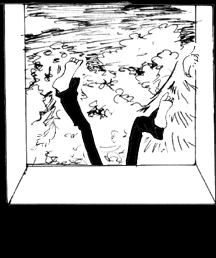 |
その時です
「つかまえた!!」
窓の外からなつかしい声が聞こえました。
小説家は腰が抜けてしまいました。
料理されたと思っていた聴きなれた友人達の声がするのです。
「鳥!いた!」
「これであいつも安心して小説が書けるな!」
「やっぱりちゃんと近くまで戻ってくるんだねぇ。」
小説家は走って、窓から身を乗り出して外を見下ろしました。
そこには、なつかしい3人の顔がありました。
実は、3人がいなくなったのは、鳥を探しに行っていたからだったのです。